母は、子どもたちが勉強で遅れをとらないよう、対策していたと言います。
勉強面で母がしていた対策。
母がしていた対策。
『学校の勉強より先取りすること。』
子どもの頃は、公文式の教室に通っていました。
授業がどこまで進んでるかなんて、クラス単位でも違いますもんね。
妹は、一度習った漢字を、もう一度やった記憶があると言っていたし、私はそろばんを習った記憶がありません。
なんと算数の範囲が、1学期と2学期で真逆。すっぽり1学期分、抜けた部分と重複した部分とがあったそう。
明らかにマイナスですが、重複していた範囲は、先に授業内容がわかっていたことで、お友だちに教えることができて、自信になった、という側面もあったよう。
母のおかげですっぽり抜けた部分も、出遅れずに済みました。
妹も私も、教えられる側でいたい、と、勉強で遅れをとりたくない気持ちを、口にしていたそうです。
中学生になると、学校によって、地理と歴史を同時進行で進めているところや、1年生は地理、2年生は歴史、と分けて進めるところなどもあったそう。
そういう情報を得ながら、引越しのタイミングなどを、考えていたそうです。
(父の単身赴任先に着いて行く為、不動産屋さんに良い土地や物件情報があれば連絡して欲しい、と伝えていたとのこと。)
ある副教科の先生には、

やっぱり一年生からいる子にいい成績つけてやりたい。
なんてことも言われ、悔しい思いもしたそうです。
(問題発言ですよね。笑)
2年生から転校してきた私は、不利ではないか!
授業内容のズレや、副教科なんかの面では、内申点で損しているところがあったと思います。
もうひとつ、母が意識していたことは、
『得意を見つけてあげること』。
“1つできると、他も引っ張られる“
ひとつできると、バランスを取るように他もできるようになる。
この記事を書くにあたって、母や妹に話を聞いたのですが、これは良いこと聞けたな、と思いました。
自分の子どもたちにも、同じように、何か見つけてさせてあげたい。
自分の子どもたちに経験させたいか。
転校は嫌いではなかったです。
一度リセットされるのがイヤじゃなかった。
将来の糧になっている部分もあります。
私の父と祖父は、仕事の事情で離れている期間が長かったようで、母からは、父が祖父に気を遣っているように見えていたそうです。
(実際はわかりませんが。)
なるべく親子一緒の時間を、長く過ごす方がいいのかな。
そう思うと、自分の子どもたちとは、転校してでも一緒にいる方がいいかな。
こればかりはわからないので、家族で相談して決めるしかありませんね。
でも、勉強面のこと、お友だちのことを考えると、しても小学校中学年くらいまでにしたいかな、とも。
地元の幼なじみとずっと仲良し、今もみんなで会っている、とか、少し羨ましかったりもするのです。
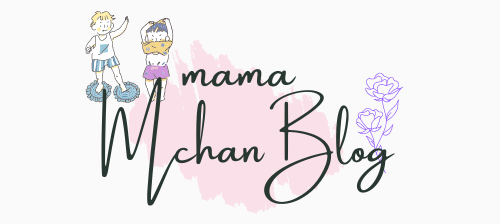

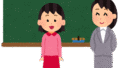
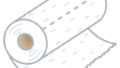
コメント